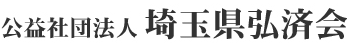【 比企支部の紹介 】
比企支部は、埼玉県のほぼ中央部に位置する東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町で構成される地域で活動しています。田園地帯から、秩父山系を背景に置く丘陵地帯まで緑豊かな風光明媚なところをフィールドとしています。
令和5年度
○セミナー事業(親睦事業)
令和5年1月19日、セミナー及び情報交換会を吉見町において「鎌倉殿を支えた比企一族」をテーマに開催しました。参加者は14名でした。
講師には「比企一族歴史研究会」会長の西村裕(ゆたか)先生をお招きしました。「比企」の名称を全国的に知らしめたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の最終回放映終了の熱が冷めやらぬこの時期にこの分野の第一人者にお話を伺いました。
平治の乱(1159年)で平清盛に敗れ、伊豆に流された源頼朝を物心両面で世話をしたのが比企の尼(比企能員の母の姉)と云われています。また、北条や畠山らとともに平家討伐の旗を上げた頼朝を支えたのが比企一族でした。さらに頼朝の子頼家の妻が比企能員の娘である若狭の局であり、北条政子とも親しかったこともあり鎌倉幕府の成立その後に歴史に大きく関与しました。しかし悲劇がおきました。大河ドラマでも描かれたとおり頼朝没後の幕府は13人の合議制となり、御家人同士の勢力争いの中で比企能員は北条時政に討たれてしまいます。
西村講師は、この比企の乱と呼ばれ比企氏が謀反を企てたので北条がそれを収めたとされる歴史を比企の側から吾妻鑑以外の文献から反論しました。さらに東松山市の宗悟寺、正法寺、川島町の金剛寺、滑川町の三門館跡など比企氏ゆかりの名所旧跡を詳しく紹介していただきました。
○道路清掃活動(地域支援事業)
第1回を6月29日(参加者14名)、2日目を11月9日(参加者10名)、東武東上線高坂駅西口から県立こども動物自然公園までの2km道路(県道含む)の清掃活動を実施しました。この事業は比企支部全会員に呼びかけ、令和元年から春と秋の年2回継続的に行っています。
東松山県土整備事務所の協力をいただき、トングやゴミ袋をお借りして2組に分かれて歩道のゴミ・空き缶を拾い集めます。6月は沿道の植え込みに雑草が多く茂り、また11月は落ち葉が堆積しています。すべて片づけるのは大変ですが、たばこの吸い殻や菓子の空き袋、ペットボトルなど参加会員が熱心に拾い集めました。
道路清掃活動を通じ、地元の環境を整備し、県立こども自然公園を訪れる人々を歓迎し地域に少しでも貢献できればと思っています。




○赤い羽根共同募金活動(地域支援事業)
10月1日、東武東上線東松山駅頭にて、会員9名が 参加して赤い羽根共同募金活動を行いました。朝9時から2時間の活動でした。東松山市社会福祉協議会と連携し、のぼり旗、募金箱等をお借りして、駅を利用する市民に声掛けを行い募金に協力をお願いしました。
参加して赤い羽根共同募金活動を行いました。朝9時から2時間の活動でした。東松山市社会福祉協議会と連携し、のぼり旗、募金箱等をお借りして、駅を利用する市民に声掛けを行い募金に協力をお願いしました。
今年は、日曜日の朝、それも雨が降り、市民体育祭等行事が中止になるところが多く、人出はまばらでした。それでも、残暑厳しかった9月から10月に日附けが変わり急に秋めいた中で季節感ある募金の声掛けに、快く応じてくださった家族連れの方々からは秋の行事が重なるこの日曜日に大変ですねとねぎらいの言葉をいただきました。年の瀬を感じさせるこの行事も時代とともに変化していると感じました。